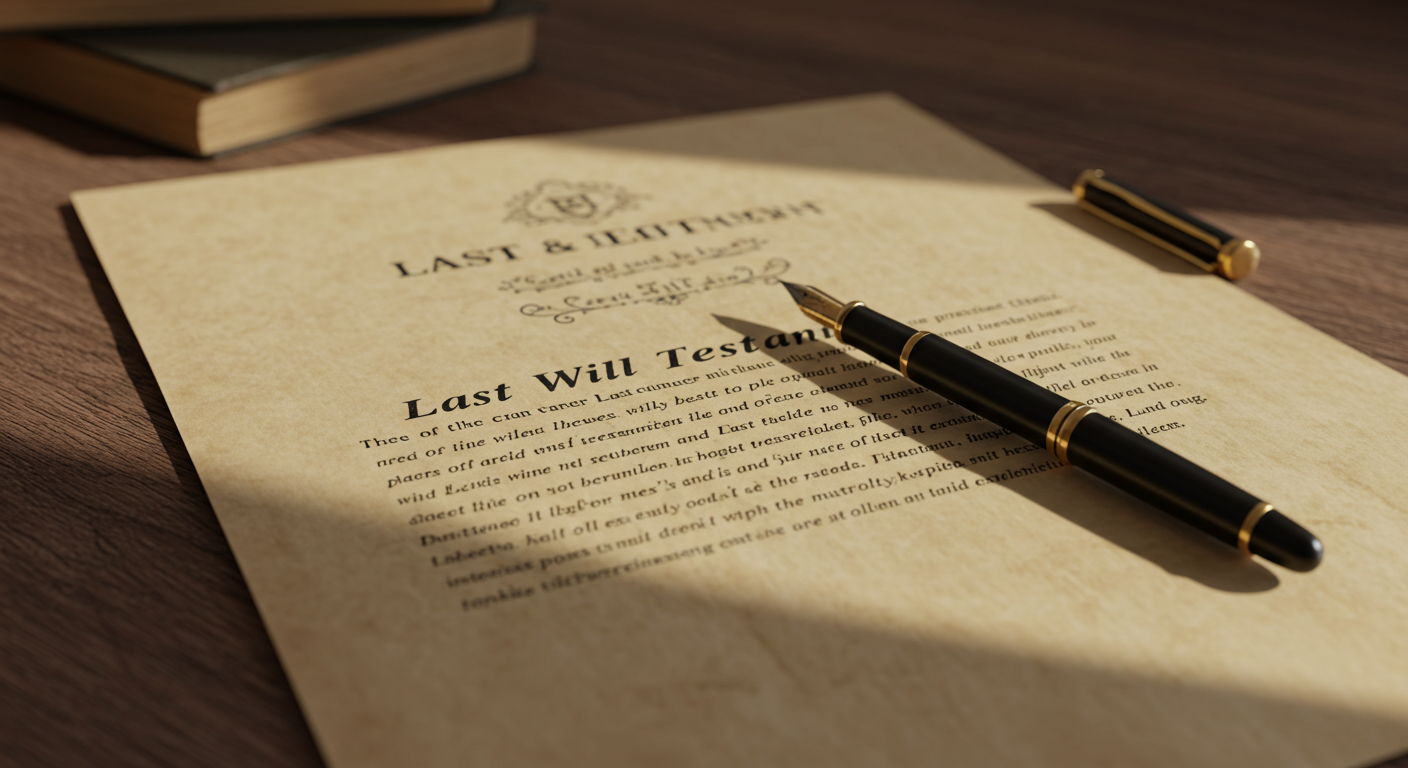相続について、皆さんがお持ちの疑問にお答えするために、民法の規定を説明し、並行して実務上のポイントなども解説していきます。
今回は第3回です。前回から「法定相続」という相続の基本的なルールを説明しています。
今回は、「相続財産」について説明していきます。
「相続財産」って「亡くなられた方(被相続人)が持っているものすべて」ではないのか、と思われる方もいらっしゃると思います。しかし、中には相続財産にはならないものもあるのです。
相続人の権利は包括承継が原則だと前回お話ししました。以下はその包括承継の原則の例外として決まられているルールです。
①亡くなられた方(被相続人)の一身専属的な権利や義務(その地位)
●被相続人が公営住宅に居住されていらっしゃった場合の「公営住宅使用権」がこれに当たります。民間住宅の賃借権は相続の対象なのですが、公営住宅の場合そのまま居住する権利が相続財産とならないケースもあるので、注意が必要です。(注1)
●被相続人の「親権」という権利・義務もこれに該当すると解釈されます。
②祭祀に関する権利
●墓地、仏壇仏具、位牌などは、相続の対象にはなりません。「祭祀主催者」が承継するとされています。被相続人の遺言で指定されていなければ、「慣習に従う」(民法897条1項)と規定されています。慣習が不明な場合は、家庭裁判所が定めることになっています。
③死亡保険金請求権(負相続人以外の方が受取人の場合)
●被相続人が自らを受取人にしている「生命保険死亡保険金」は、相続財産です。しかし、被相続人以外を受取人に指定していた場合は、その受取人の固有財産ということになります。
④死亡退職金や遺族給付
●被相続人がなくなられたことでお勤め先だった企業から支払われる「死亡退職金」や「遺族給付金」は、通常その企業の退職給与規定などに受取人が指定されていることが多いです。この場合は、相続財産ではなく、受取人の固有財産ということになります。「死亡退職金」「遺族給付」等は、受取人である遺族の生活を保障するという目的で各企業で規定されている仕組みであると考えられることがその理由となっています。判例でもこのことが裏付けられています。(注2)
⑤香典や弔慰金
●これらは喪主に対する贈与であり、相続財産ではないという解釈が通説です。ただし、だからと言って葬儀費用も喪主の負担ということではありません。葬儀費用は相続財産の負担とすべきだというのが通説です。
次回は、法定相続では相続財産をどのように分配するルールになっているのかという「相続分」について解説します。
(注1)
公営住宅は、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするもの」と法律で定められているというのが、当然に相続の対象とはならないと判決された趣旨です。(最高裁平成2年10月18日判決)
(注2)
死亡退職金の受給者について、民法の法定相続の順位と異なる支給方法が決められている場合、死亡退職金の受給権は相続財産には属さず、受給権者たる特定の遺族がその方固有の権利として取得するとされました。(最高裁昭和58年10月14日判決)