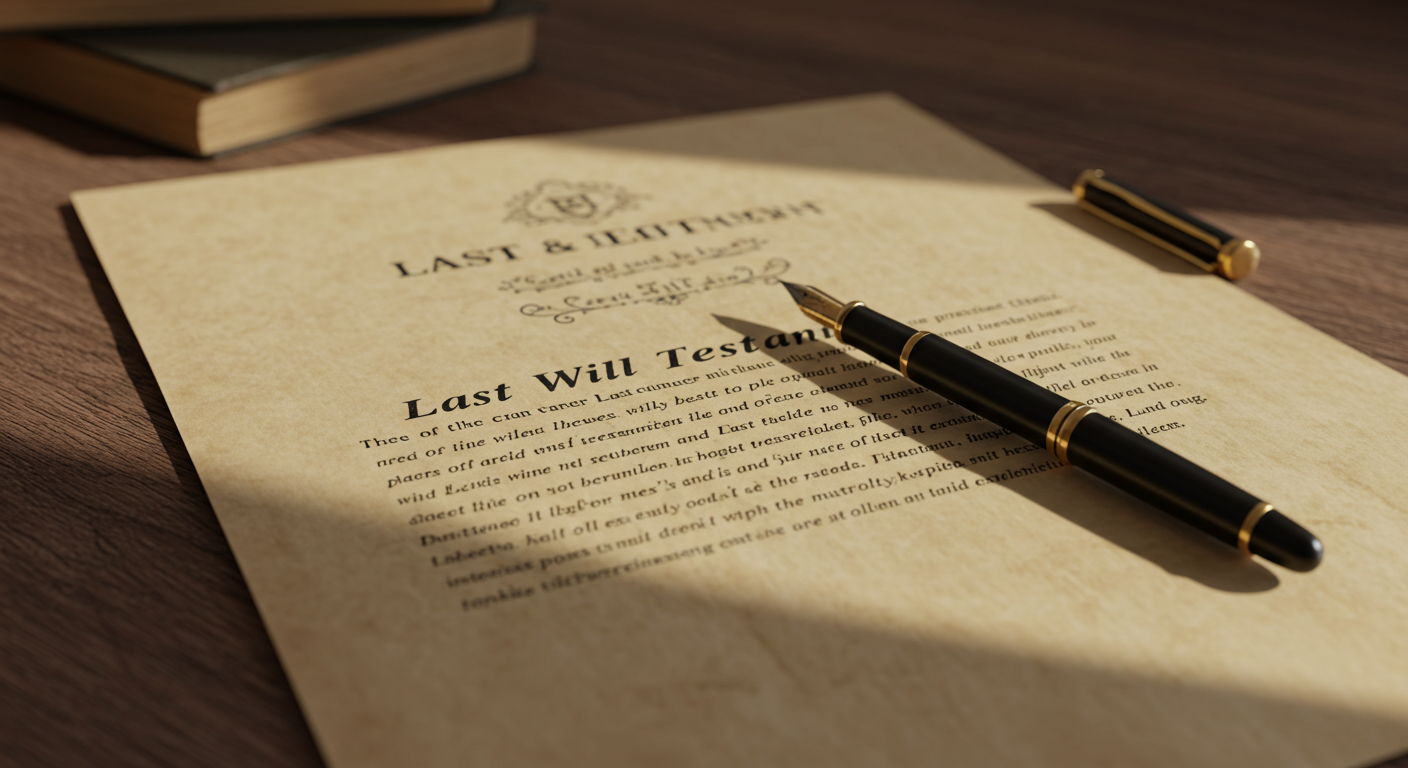相続について、皆さんがお持ちの疑問にお答えするために、民法の規定を説明し、並行して実務上のポイントなども解説していきます。
今回は第4回です。現在「法定相続」という相続の基本的なルールを説明しています。
今回は相続では相続財産をどのように相続人で分配するルールになっているのかという「相続分」について解説します。
第2回で説明した、法定相続人の範囲と順位を覚えていらっしゃるでしょうか。そこで説明した法定相続人に「法定相続分」という割合が規定されています。
ただし、第1回で説明したように、遺言で相続分の指定があればその指定が優先されます。これを「指定相続分」と言います。
さらに、被相続人から過去に一定の贈与や遺贈(注1)を受けた方がいらっしゃった場合、あるいは被相続人に特別の貢献(寄与)をした方がいらっしゃった場合、これらの贈与・遺贈・寄与が考慮されて、具体的な相続分の額が決められるというのが法定相続ルールの基本的な構造です。これを「具体的相続分」と言います。
① 法定相続分
<ケース1>配偶者と子供
●配偶者が1/2、子ども全員で1/2です。子供が複数いらっしゃれば、子どもたちで全体の1/2を均等に配分します。
●第2回でお話しした代襲者の場合は、亡くなられたお子さん(被代襲者)の相続するはずだった割合を代襲者が受け取ります。代襲者が複数いらっしゃる場合は、非代襲者の割合をさらに代襲者複数人で均等に配分します。
<ケース2>配偶者と被相続人の親(その親)
●配偶者が2/3、被相続者の親及びその親全員で1/3です。親及びその親が複数いらっしゃる場合は、やはり均等に配分します。(注2)
<ケース3>配偶者と兄弟姉妹
●配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4です。兄弟姉妹が複数いらっしゃれば、全員で均等に配分します。
●ただし兄弟姉妹の中に被相続人と両親の一方のみが同じという方がいらっしゃった場合は、その方の相続分は被相続人と両親双方が同じ兄弟姉妹の方々の半分となると規定されています。
<ケース4>配偶者のみ
●配偶者が相続財産の全部を単独で相続します。
<ケース5>配偶者以外の相続人のみ
●配偶者がいらっしゃらない場合は、配偶者以外の相続人の順位の順番でその順位の方々が相続財産の全部を均等に配分します。
② 指定相続分
●相続の指定とは、亡くなられた方の遺言で「誰に、何を、どのように相続させるか」を指定するケースのことを言います。このケースで考慮しなければならないのが「遺留分」です。
●「遺留分」とは、兄弟姉妹(と代襲者)を除く相続人に認められている相続財産の一定割合を承継できる利益のことを言います。遺言の事由は原則として認めながらも、相続人の生活を保護する趣旨で定められたルールです。ただし、第2回でも説明した「相続欠格」「廃除」「相続放棄」により相続権を持っていないものには認められません。
●「遺留分」の割合は、基本的には「配偶者」と「子や孫」の場合は法定相続分の半分、「親やその親」の場合は1/3となっています。遺留分に反する相続分の指定があった場合には、その相続人に「遺留分侵害額請求権」という権利が発生します。
③ 具体的相続分
以上の法定相続分と指定相続分などを考慮して、やっと「具体的相続分」にたどり着きます。
ここでは以下のものをさらに考慮していきます。
<特別利益>
特別利益とは、亡くなられた方(被相続人)から相続人に遺贈された財産や「婚姻、養子縁組、生計の資本の目的」で贈与されたものを言います。(民法903条1項)
●「婚姻の目的」の例としては、結納金やお祝い金が当たります。挙式費用は通常の範囲であればこれには当たらないとされています。
●「生計の基本の目的」とは、子どもに親が宅地や家屋を贈与した場合などが当たります。通常の親の扶養義務の範囲を超えていると認められるものもこれに当たる可能性があります。
●さらに付け加えると、この特別利益の中の贈与分は相続財産の一部として加算され、「みなし相続財産」という金額が産出されます。実際に相続の時点に残っている被相続人の財産ではないものの、特定の相続人に特別に送られた利益なので、相続人全員の公平性を保護する趣旨から、このように「みなし相続財産」というルールが設けられています。
<寄与分>
亡くなられた方(被相続人)の財産の維持または増加について特別の貢献(寄与)をした相続人の方がいらっしゃった場合の相続分を言います。
●「寄与」の形には以下のようなものがあります。「事業の手伝い」「金銭等の支援」「療養看護」「扶養など」などです。この寄与が「特別な寄与」だと認められるには、「相応の対価を得ていないこと」と「通常期待される程度を超えてていること」が求められています。被亡くなられた方を扶養していたというだけでは「特別な寄与」には当たらないでしょう。
●相続人以外の親族の方がこのような「寄与」をした場合にもルールが設けられています。相続がされた場合に、特別な寄与を行ったと認められるその親族は、相続人に対して「特別寄与料」を請求することができるという制度です。この金額は協議で定めるとされています。
以上、相続財産の相続分について解説しました。次回は、相続の承認と放棄について説明します。
(注1)
「遺贈」は亡くなられた方(被相続人)が他人に財産を贈ると遺言されたことを言います。遺贈を受ける方を「受遺者」と言います。(民法964条)
(注2)
例えば、子どももその代襲者もいらっしゃらない被相続人で、その両親がいらっしゃる場合は、その両親が相続人です。またその両親ともにいらっしゃらない場合に被相続人の祖父母世代の方がいらっしゃれば、その方々が相続人となります。
ただし、被相続人の両親のどちらかでもいらっしゃれば、祖父母の世代の方が相続人になることはありません。被相続人に近い世代が優先されるルールです。