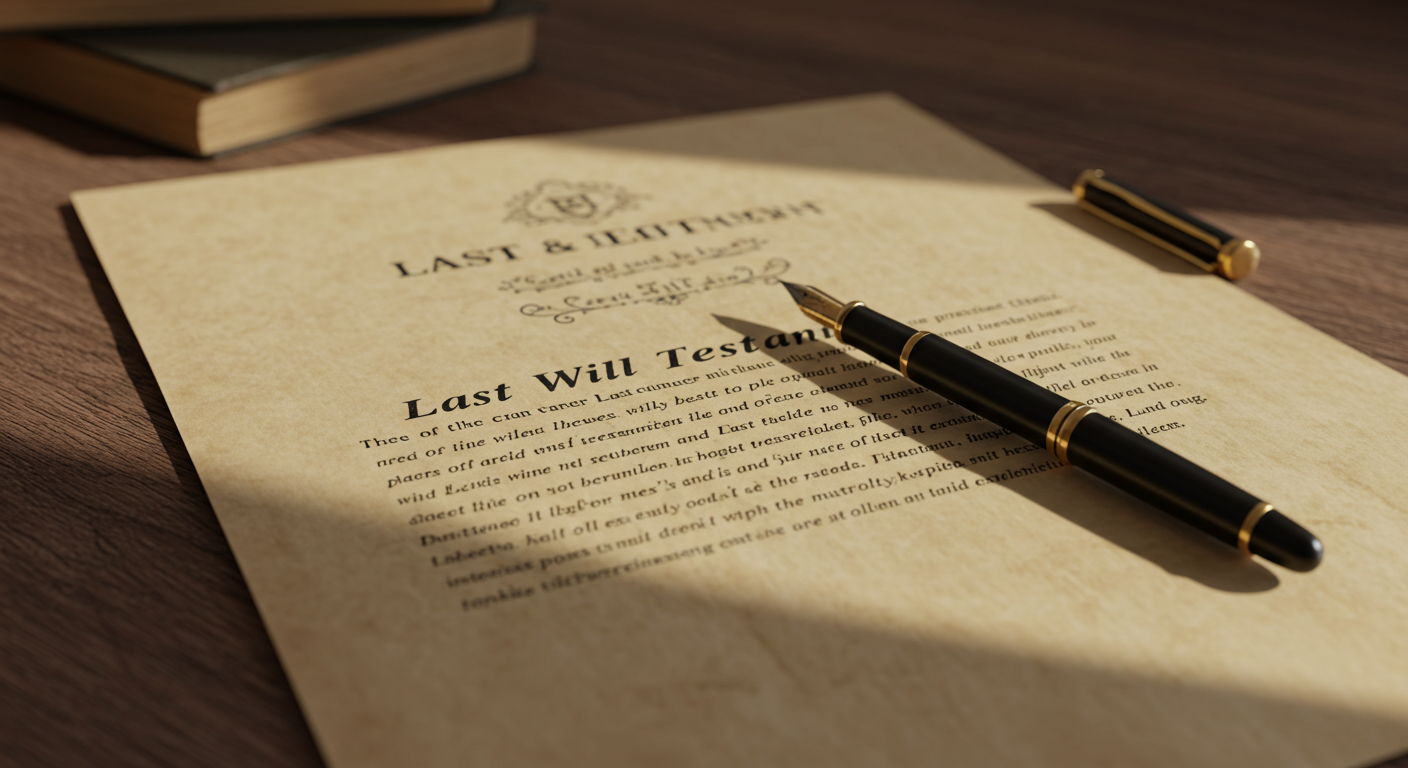相続について、皆さんがお持ちの疑問にお答えするために、民法の規定を説明し、並行して実務上のポイントなども解説していきます。
今日はその第1回です。
まず、相続の2つの形をお話しします。
「遺言のあるケース」と「遺言のないケース」の2つです。
皆さんは、原則として法律で相続をすることができる範囲と割合が決まっていて、その形を故人(被相続人)の意思で修正することができるのが「遺言」だと思っていらっしゃるかもしれません。
しかし、実は民法という法律が定めるルールに沿って行う相続の形はあくまで「遺言のないケース」を補うものであって、原則は「遺言書のあるケース」のケースなのです。(注1)
故人が遺言という意思表示を行っていたケースは、その遺言に従って財産は承継されることになります。これが原則なのです。法定相続とは異なる内容の遺言でも、民法に定められた方式で行われた遺言であれば、もちろん有効です。
ですので相続が発生した際には、まず遺言が存在するかどうかを確認ください。
もちろん遺言のないケースも普通にあり得ます。その時は民法の定めるルールに従って財産が継承されます。これが法定相続と言われるものです。
ただし、遺言の自由の原則には制限があると民法で規定されています。
「遺留分」という、ある条件を満たす相続人に求められている最低限の取り分のようなものです。
例えば配偶者がすでに亡くなっていてお子さんが1人いらっしゃる方がお亡くなりになり、その方が「全財産を最後まで私の面倒を見てくれていた友人である〇〇〇に譲る」という遺言を残していたとします。
このようなケースでは、お子さん1人が「遺留分」という財産を相続する最低限の割合を持っていて、その権利が侵害されているので、「遺留分侵害額請求権」という権利を取得すると民法に規定されています。「遺留分」については、第4回でも説明します。
次回は、まず法定相続のルールから解説します。
(注1)
法律はその条文に規定されている内容そのものだけでなく、裁判所が具体的な裁判の中で法的な判断を下した「判例」や、最高裁判所が重要な法的解釈について決定を下した「最高裁大法廷決定」なども重要な意味を持っています。第1回で説明した内容は、「法定相続は補充的機能にとどまる」と最高裁が平成25年9月4日に決定した判断に基づいています。