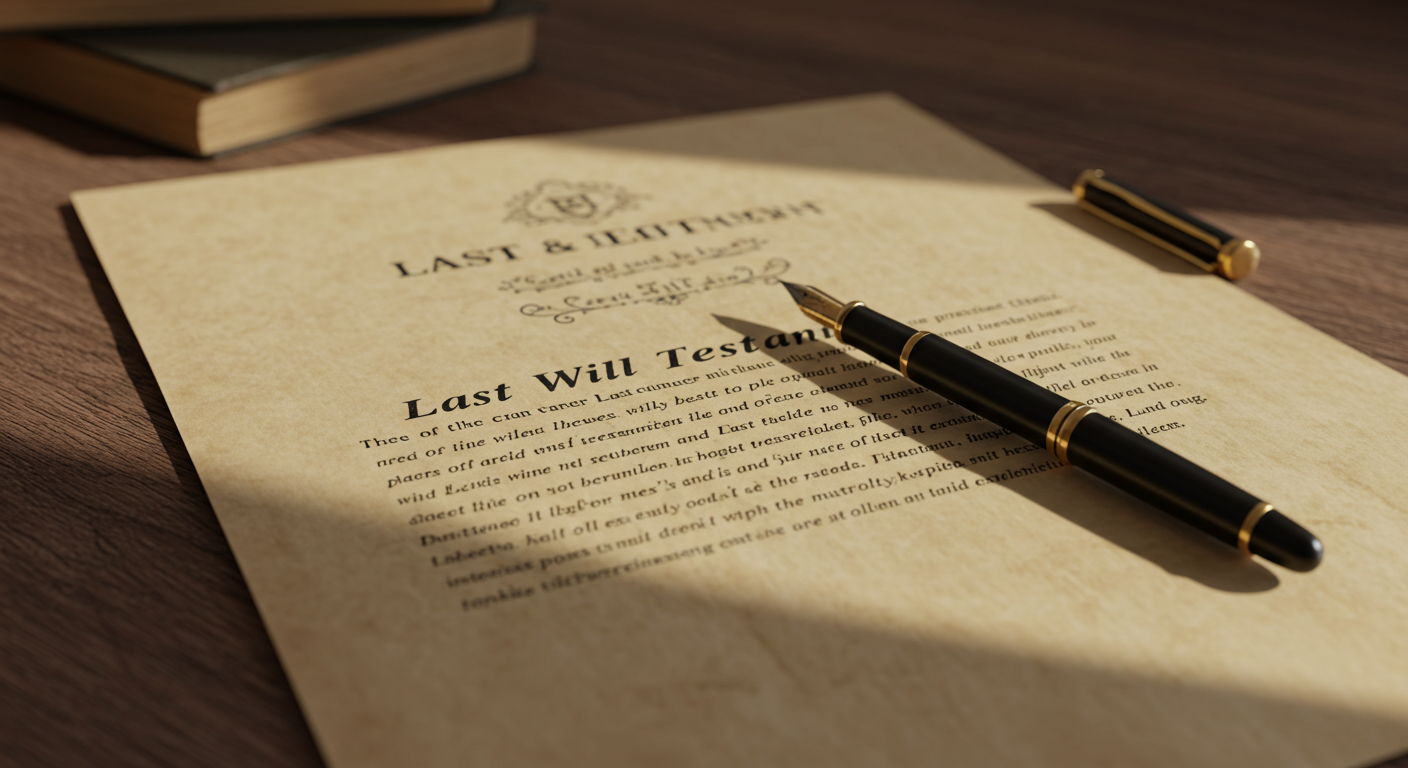前回は「仏教には「仏」「法」「僧」の三宝という三つの要素を持つという特徴がある」ことをお話ししました。今回はその中の「法」いわゆる教えの内容の特徴(法印と言いますが)についてお話しします。
お釈迦さまの出家の目的
仏教は2500年の歴史を経て多くの宗旨宗派に分かれてきました。しかし、そのエッセンスはお釈迦さまが説かれた不変の真理にあります。お釈迦さまが現実の苦悩からの解脱を説かれたその根本的な原理です。
もともとお釈迦さまは、なんの不自由もない王子として、2500年ほど前にネパールとインドの国境辺りに在った王国にお生まれになりました。
しかしお若いころから現実に私たちが日々感じている「生老病死」(注1)や「愛別離苦(愛する人・モノとの別れの苦しみ)」「怨憎会苦(嫌いな人・モノとも付き合わなければいけない苦しみ)」「求不得苦(欲しくて求めるものが手に入らない苦しみ)」など人生を生きていれば常に直面しなければならない「人生の苦しみ」の不条理を強くお感じになられていたようです。
お釈迦さまは「人生は苦そのものである」(「一切皆苦」と言います)(注2)ととらえられて、更にその「苦」の原因には「煩悩」があるのではとお考えになり、「煩悩」を制御することによる人生の苦からの解脱(解き放たれること)を目指されて出家されました。(注3)
お釈迦さまが仏陀(ブッダ、目覚めた人)になられる
出家されたお釈迦さまは、思考を止める瞑想により煩悩から離れようとされたり、体を痛めつける苦行により強い精神力で煩悩を制御されたりしようとされますがうまくいきません。
その後、思考を止める瞑想や苦行では煩悩を制御できないと気づかれたお釈迦さまは、人の煩悩とそこから生まれる苦にかかわるすべてをありのままに観察するという瞑想(如実知見と言います)に入られました。そこでお気づきになった内容が、仏教の教えのエッセンス「法印」(「三法印))です。
一つ目、「諸行無常」印
平家物語の一説でも知られる「諸行無常」という言葉が、最初の仏教の法印です。単に「無常」と書かれているお経(経典・聖典)もあります。
「諸行」とはこの世の中の森羅万象一切のことを言います。お釈迦様は、この世のすべての現象には原因があると考えられました。当たり前と言えばそれまでですが、苦しみの原因は、この当たり前のことが見えなくなっていることにあるとお気づきになられたのがお釈迦さまです。一切の現象は原因(「因」)があって、ある条件(「縁」)の下で、生まれてくる(「果」)のだから、原因と条件が常に変化している世の中で、生まれてくる結果だけが変化しないということはありえないことを如実に知見されました。目の前にある現象は、時間の経過とともに常に変化し続けているのだ、と気づかれたのです。天体の星々も、庭の草花も、自身の身体も、常に変化していて、昨日のまま、1時間前のまま、1秒前のままの現象は無いのだと冷静に客観的に観察されたのです。
身体だけではありません。自分の頭の中の記憶や思考、心の中の感情も、昨日のままではありません。
お釈迦さまは、「人生は無常であるがゆえに苦である」と、はっきり目覚められたということだろうと思います。でも、決してだからと言って厭世観にとらわれて、この世は無常だから無駄だと世捨て人になられたのではないところが、お釈迦さまのお釈迦様たるところだと思います。
すべては自分で制御しきれない原因や条件で生まれていること、すべては有限で限定的であること、しかしそんな無常なものを人間は恒常なものだと思い込むことが多いこと、それが「人生の苦」の原因であること、そんな状態にある人間は、真理を知らず暗闇にいて夢にうなされているような状態に等しいことなど。
お釈迦さまはこのような苦しみの暗闇から目覚められて、ブッダ(目覚めた人)と呼ばれるようになったのでした。(注4)
「三法印」の一つ目しか説明できていませんが、先も長いので今回は「三法印の一つ目、諸行無常印」についての説明でとどめておいて、次回残りの二つ「諸法無我印と涅槃寂静印」について説明します。
(注1)
「生まれることが苦しみなのか」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これには二党利の説明がなされています。一つは「生まれることは、その後のほぼ思い通りにならない人生という重荷を背負うことなのだから、人生のスタートそのものが苦しみなのだ」という説明です。もう一つは、「大人になると覚えていないけど、生まれるときの赤ちゃんは狭い産道を通って大変痛い思いをして生まれてくるんだ、赤ちゃんの産声は痛い痛いという鳴き声なんだ」というものです。私は後者の説明を採用した方が四苦八苦の理屈が合うように思うのですが、本当のところは私にもわかりません。
(注2)
上で説明しました「三法印」にこの「一切皆苦」を入れて「四法印」という表現がされることもあります。
(注3)
人生は苦であり、その原因に煩悩がある、ということは、当時のインドの多くの出家者の間で共通認識だったようです。なので、思考を停止させる瞑想の先生(師匠)も、体を痛めつけて精神力を鍛えるという苦行の先生(師匠)もたくさんいらっしゃったようです。お釈迦さまも、思考停止の瞑想の先生お二人(アーラーラ・カーラーマ先生、ウッダカ・ラーマプッタ先生)に最初は学ばれたことが伝えられています。
(注4)
「ブッダ(Buddha)」とはサンスクリット語の「budh」(目覚める)の過去受動分詞「目覚めた(者)」です。音写して「仏陀」、意味から「覚者」と漢訳されました。